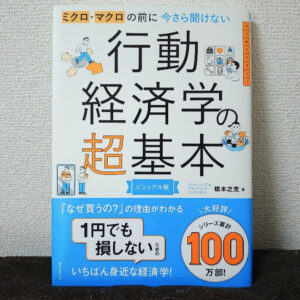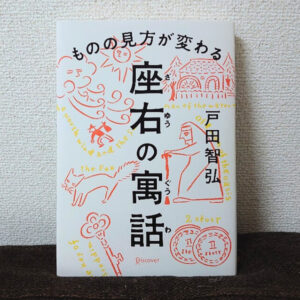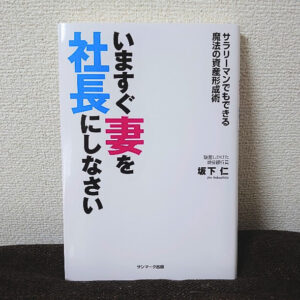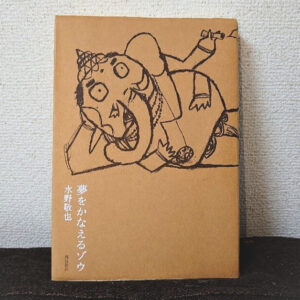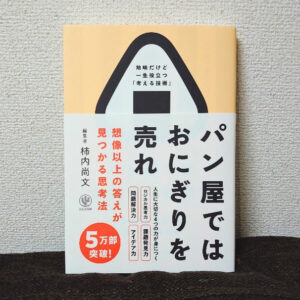積算で購入土を計上する際の土量計算をざっくりと解説します。
なお締固め率C=0.9、ほぐし率L=1.2として計算していきます。
最初に結論を言うと、盛土後や埋戻後の土量として100m3必要であるとき、積算上にて計上すべき購入土の土量は
100/0.9×1.2=133m3
となります。
順番に計算していきましょう。
まず盛土後(埋戻後)に100m3必要ということは、締固めた後の土量が100m3であるということになりますよね。
締固め率C=0.9とした場合、必要な購入土の地山土量は
100m3/0.9=111.11・・・≒111m3となりますよね。
この計算にて、埋戻後に必要な購入土の地山土量は111m3であることがわかったかと思います。
これで終わってはいけません。
購入土というものは、ほぐされた状態の土です。
そのため、先ほどの計算にて算出した地山土量111m3にほぐし率L=1.2を乗じます。
111m3×1.2=133m3
よって上記条件にて必要な積算上の購入土の土量は133m3となります。
わかりましたでしょうか。
積算にて購入土を計上する際は、数量の算出に注意しましょう。
・あわせて読みたい
>>>「土木施工管理技士 おすすめの問題集・過去問と作文作成代行」
>>>「土量計算(土量変化率)を解説【間違えやすい例題付き】
」
>>>「効率の良い土木の勉強方法」