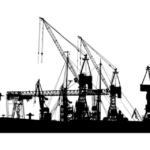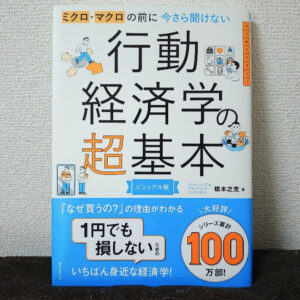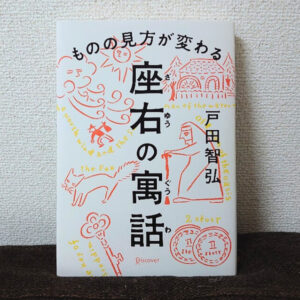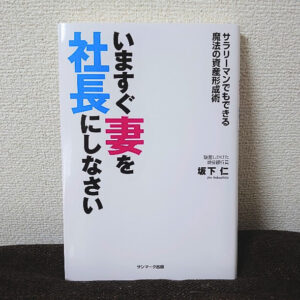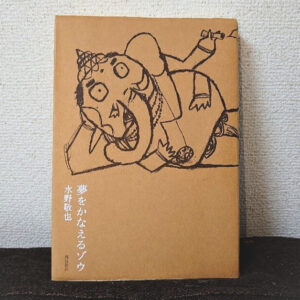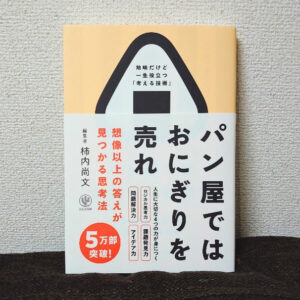公共工事の積算や数量算出でよく出てくるコンクリートの「無筋構造物」と「小型構造物」の違いをざっくりと解説しています。
どちらもよく似た名称ですが、はっきりとした使い分けがされています。どうぞご覧ください。
無筋構造物と小型構造物の違い
コンクリートの「無筋構造物」と「小型構造物」の違いは明確に定められています。
まずは国土交通省や都道府県・市町村などの自治体にて使用されている「積算基準」に明記されている違いは以下のとおりです。
無筋構造物:マッシブな構造物、比較的単純な鉄筋を有する構造物、均しコンクリート等
小型構造物:コンクリート断面積が1m2以下の連続している側溝、笠コンクリート等、コンクリート量が1m3以下の点在する集水桝、照明基礎、標識基礎等
この文章だけで理解できたら、この先は読まなくてもOKです。
正直、上記の説明ではなかなかイメージでませんよね。それぞれをざっくりと言い換えてみます。
無筋構造物
重力式擁壁・もたれ式擁壁・重力式橋台・方塊ブロックなどの大きくて重量のある構造物(鉄筋無し)、ひび割れ防止の鉄筋や用心鉄筋レベルの鉄筋がある構造物(補強目的の鉄筋ではない)、均しコンクリート・ベースコンクリート・捨てコンクリートなど
小型構造物
小さな構造物・点在した構造物で細々とした型枠が必要な構造物(無筋・有筋を問わない)
もし現場打集水桝を設置する場合であれば、集水桝自体は小型構造物、その基礎コンクリートは無筋構造物となります。
イメージが付きましたでしょうか。おおよその使い分けは上記のとおりでOKですが、各自治体や処分場などで若干の取り扱いが異なります。
正式な使い分けについては、関係機関にて確認いただきますようお願いします。
・あわせて読みたい
>>>「土木施工管理技士 おすすめの問題集・過去問と作文作成代行」
>>>「セメントミルクとセメントペーストの違い」
>>>「土木の基礎知識~初心者が覚えておきたい用語まとめ~」
>>>「効率の良い土木の勉強方法」