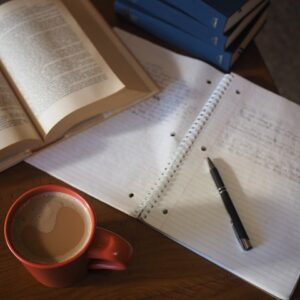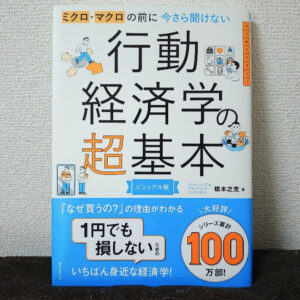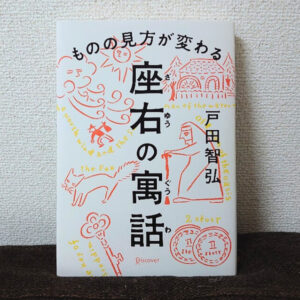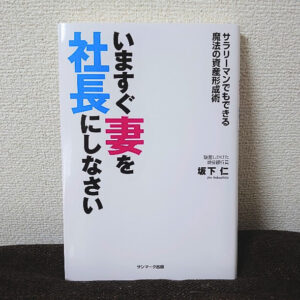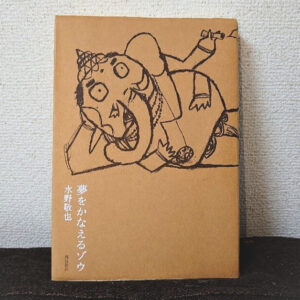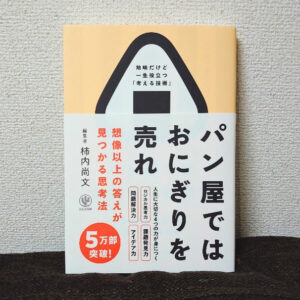ボーリングと標準貫入試験の意味や違いを、土木初心者向けにざっくりと解説しています。
それぞれよく似たような試験をしていますが、全く違う試験です。
これらの試験の意味や違いを理解して混同しないようにしましょうね。
ボーリングと標準貫入試験の意味や違い
まず最初に頭に入れておきたいのが、ボーリングと標準貫入試験はセットで行われるということです。
ボーリングとは、ざっくり言うと「地面に穴を掘る」ことです。
詳細に言うとボーリングには以下の2種類あります。
- オールコアボーリング
- ノンコアボーリング
オールコアボーリングは、ざっくり言うと掘った穴の土を全部採取します。土試料を採取するための試験です。
ノンコアボーリングは、ざっくり言うとただ穴を掘るだけです。掘った穴の土を採取しません。
最初に「ボーリングと標準貫入試験はセットで行われる」と言いましたが、詳細に言うと「ノンコアボーリングと標準貫入試験はセットで行われる」です。
・あわせて読みたい
>>>「ノンコアボーリングとオールコアボーリングの違い
」
>>>「土木施工管理技士 おすすめの問題集・過去問と作文作成代行」
標準貫入試験の説明では、よく「質量63.5kg±0.5kgハンマーを76cm±1cmの高さから自由落下させて30cm打ち込むのに要する打撃回数(=N値)を求める」とありますよね。
実はこの標準貫入試験とは、ノンコアボーリングにて掘った穴を使って行われる試験なのです。「ボーリング孔を利用した試験」と言ったりします。
「標準貫入試験でN値を求める」とありますが、それ以外に土の採取も行われます。
そのため標準貫入試験では、N値を求めて地盤の固さ・軟らかさが求められるのと同時に、「どの深さでどのような土が堆積されているか」もわかります。
よく「ボーリング試験をする」と言うことがありますが、これは「ノンコアボーリングと標準貫入試験を行う」という意味を示していることが多いです。
標準貫入試験は、土木や建築などで構造物の設置に必要とされる「地盤が強固であるか」「支持層の深さはどこか」と言ったデータを得るために行います。
これらの試験にてボーリング柱状図を作成することで、構造物の設計を行うことができます。
・あわせて読みたい
>>>「土木施工管理技士 おすすめの問題集・過去問と作文作成代行」
>>>「土木の基礎知識~初心者が覚えておきたい用語まとめ~」
>>>「効率の良い土木の勉強方法」